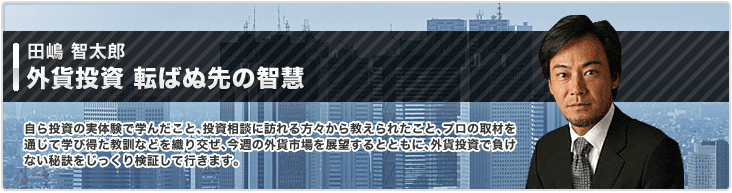先週13日、トランプ米大統領は「相互関税」の導入を指示する覚書に署名した。米政権はこれまでにカナダ、メキシコ、中国への追加関税や鉄鋼・アルミニウムへ製品に対する25%の追加関税の全面適用を打ち出しているが、相互関税についてはその影響がより広範に及ぶ。加えて、14日には自動車関税を導入する考えも示している。
とはいえ、市場はこれを比較的冷静に受け止めており、総じて「想定していたよりはずっとマシ」との感が広がっている模様。カナダとメキシコについては3月までの両国による対応次第で再延期や見送りの可能性もあると見られ、鉄鋼・アルミニウム製品については「適用除外」の余地がある。相互関税についても今後、国ごとの調査と個別の交渉という過程を経るなかで、最終的な影響は想定よりも和らげられることが期待される。
折しも、先週は1月の米消費者物価指数(CPI)と米生産者物価指数(PPI)の結果が強めに出たことで、インフレ再燃への警戒が強まり、米連邦準備制度理事会(FRB)による追加利下げが「年内は難しい」との見方も市場の一部で燻り始めている。
このような状況下では、トランプ氏も「より緩やかな関税措置を採用せざるを得なくなるのでは」、「関税と移民政策の双方においてやや穏健な措置に留めようとするのでは」との見方が市場に浮上し始めており、少なくとも過度な不安は薄らいできている。
実際、先週末にかけて米10年債利回りは4.5%割れの水準に低下しており、その動きに呼応して目先はドル/円の上昇にも歯止めがかかっている。
米債利回り上昇に一旦ストップがかかったのは、一つに今月28日に発表される1月の米個人消費支出(PCE)価格指数について、大手米金融機関が一斉にその予想を引き下げたことがあるとされる。それは1月のPPIの結果において金融部門やヘルスケアサービス部門などが非常に弱い結果であったことが主因であったと見られ、発表後に配信された各種のレポートにおいても、その多くが「ヘッドラインの数値だけを見るとインフレ懸念が強まりそうだが、PCE価格指数の構成項目は総じて抑制的だったことから、全体としてはインフレ再燃懸念を和らげる内容だった」と評していた。
また、先週14日に発表された1月の米小売売上高の結果がここ2年近くで最大の落ち込みとなったことも見逃せない。数値が大きく低下したのは、暴風雪や山火事の影響も大きかったが、加えて12月の数値がトランプ関税を見越した駆け込み消費によってかさ上げされたことに対する反動が生じた部分も大きかったと見られる。
よって、なかには「2月は回復する」と見る向きもあるようだが、12月に駆け込みで増加して1月に大きく減少したのは主に耐久消費財であり、そこで生じた需要の先食いの影響は今後も尾を引くと見ることもできるだろう。
トランプ関税に対する過度な警戒が後退しているとはいえ「米政権の政策運営の行方に関する不確実性が高過ぎることが何よりの問題」であることに変わりはない。今しばらくは、FRBの様子見姿勢や米金利の高止まり、米インフレ警戒を背景にドルを売り仕掛けることに慎重さが求められる状態は続くだろうが、いずれは米国経済の先行きに暗雲が漂い始め、次第にドル離れが加速する可能性も十分にあると思われる。
つまり、ドル/円の上値は自ずと限られたものになり、当面は戻り売りを基本姿勢に臨みたいと個人的には考えており、とりわけ週足ロウソクが一目均衡表の週足「雲」や62週移動平均線をクリアに下抜けてきた場合は、そこから下値リスクへの警戒を強めることは求められると心得ておきたい。
諸事情により、本稿の更新は今回が最後。「第928回」を数えるまで、長きに亘ってご愛読いただいた皆さまと、サポートしていただいたスタッフ諸氏に心より感謝申し上げるとともに、皆さまの益々の弥栄をお祈り申し上げて「転ばぬ先の智慧」を了する。
(02/17 07:00)
FX・CFD・証券取引・外国為替のことならマネーパートナーズ -外為を誠実に-