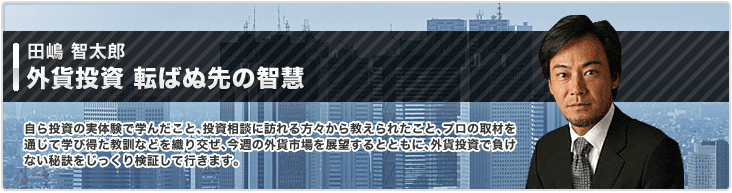前回更新分の本欄で、筆者は「カナダやメキシコなどに対する関税賦課の計画に変化が生じるのかどうかを見定めないことには、米金融政策の方向性も定めようがない」と述べた。そして案の定、先週行われた米連邦公開市場委員会(FOMC)の声明と後の記者会見におけるパウエル米連邦準備制度理事会(FRB)議長の発言には、そうした状況を背景とした微妙でどっちつかずのニュアンスが滲んでいた。
市場では、今回の声明からインフレに関する文言が削除されたことに刮目する場面が一時的にもあったわけだが、後にパウエル氏は「特に何かを示唆するものではない」と説明していた。少なくとも、その時点では「まだ曖昧にしておきたい」との思いがFOMCメンバーの間で共有されていたものと思われる。
実際、週末31日には一部メディアが「加墨への関税は3月1日から」などと報じたことで一時的にも米債利回りが低下してドルが売り戻される場面があったものの、ほどなくホワイトハウスが「2月1日からスタート(中国に対しても追加関税)」と正式に発表したことで、一転してドル買いの流れが強まるという一幕があった。
結果、市場では関税が米物価高につながるとの見方が強まり、米10年債利回りは一時4.58%まで上昇。ドル/円は再び155円台に乗せる動きとなり、そのまま高値圏でもみ合いながら155.20円処で週を終えている。
先週は、米国への輸入品に対する新たな一律関税を巡って、トランプ米大統領が「2.5%より『大幅に高く』設定したい考えを示した」と伝わる一幕もあった。後に、米商務長官候補のハワード・ラトニック氏が「国ごとに実施することが望ましい」との(一律関税とは少々距離を置いた)考えを示してはいたものの、いまだ“トランプ関税”の行方が不透明なままであることは確かである。そのため、当面は一層の関税強化が米物価を押し上げる懸念が市場に燻り続けることとなり、市場ではドル売りにポジションを傾けにくいムードが漂うこととなろう。
ただ、米物価の先行き上昇懸念が強まれば、それだけ米景気の拡大余力が損なわれる可能性が高いこともまた事実。特に、足元で堅調に見える米消費の勢いが今後明らかな減速傾向を辿り始めるとなれば、追って各種のソフトデータも悪化傾向を強める可能性が高まるという点は見逃すことができない。
先週30日に米商務省が発表した昨年10-12月期の実質GDP(速報値)は前期比年率2.3%増と、事前予想ならびに前回実績を大きく下回ったものの、個人消費だけは同4.2%増と突出して強い結果であった。周知のとおり、その点については市場やメディアから「トランプ政権発足前の駆け込み消費」との指摘がなされており、その実、消費の内訳では耐久消費税の伸びが12%増と異様に高かった。
これを需要の先食いと捉えるならば、後に必ずやその反動が生じる。その意味で、今後発表される1月分以降の米消費に関わる各種関連データからは目が離せないし、意外なほど弱めの結果が示された場合、市場は素直にドル売りで反応する可能性もある。むろん、FRBの政策方針にも変化が生じるものと見ておかねばなるまい。
一方、先週は一時的にもドル/円が153円台まで下落する場面もあった。その一因と見られるのが、30日に一橋大学政策フォーラムで講演した氷見野日銀副総裁の発言である。副総裁は、いまだ実質金利が極めて低い水準であることに触れ、その点については1月の政策会合後の植田日銀総裁も触れていたのだが、市場はややタカ派寄りの印象をもって受け止めた模様である。
今週は、本日(3日)に日銀の「主な意見」が公表され、6日には田村日銀審議委員が金融経済懇話会で講演することから、あらためて「市場で追加利上げへの警戒感が強まるかどうか」を見定めることが重要であると心得ておきたい。個人的には、ドル/円について戻り売り方針で臨みたいと考える。
(02/03 07:00)
FX・CFD・証券取引・外国為替のことならマネーパートナーズ -外為を誠実に-